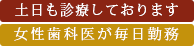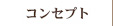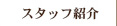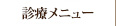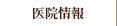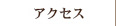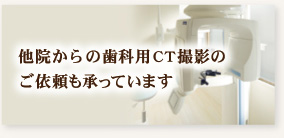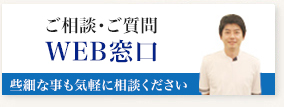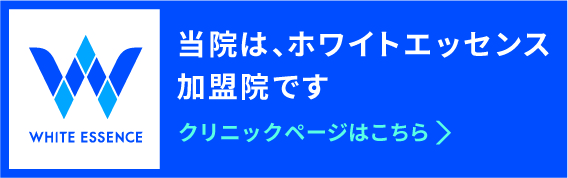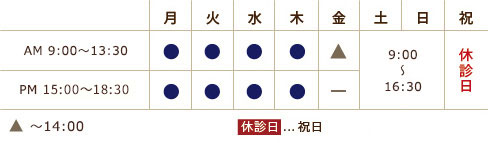根管治療はなぜ長い?治療期間が長い理由と、治療を受けたほうがよい理由
こんにちは。東京都板橋区大和町、都営三田線「板橋本町駅」より徒歩30秒にある歯医者「アース歯科クリニック」です。

「根管治療はどうして治療期間が長いの?」と疑問に思ったことはありませんか。虫歯が神経まで達したり事故などの外傷で神経が露出したりした場合、歯を残すために根管治療が必要になります。
しかし、根管治療が1回の通院で終わることは基本的になく、複数回の通院が必要です。治療に通うのが面倒に思う方も多いかと思いますが、治療が長引くのには理由があります。
本記事では、根管治療が長くなる理由と、治療を途中でやめてはいけない理由などを解説します。根管治療について理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
根管治療とは

根管治療とは、虫歯が進行してしまい歯の神経が炎症を起こしたり感染した際におこなう治療です。歯の内部にある根管から神経や感染組織を取り除き、きれいに洗浄・消毒した後に薬剤を詰めて密閉します。
根管治療が完了したら、最終的に被せ物をして歯の機能を回復させます。
根管治療が必要になった場合、治療が完了するまでに時間がかかるのが特徴です。根管治療が必要になるのは、虫歯が神経まで達している場合や、外傷などによる歯の破折によって神経が露出した場合が挙げられます。過去に根管治療した部分の再治療でも行われます。
根管治療は時間がかかりますが、適切におこなうことで歯を残せる可能性が高まります。治療の負担を増加させないためにも、早めの受診が大切です。
根管治療の期間

根管治療は、完了までに2週間〜1か月ほどかかるのが一般的です。感染した神経や組織を取り除き、根管内を洗浄・消毒し清潔な状態にする必要があるため、期間が長くなる傾向にあります。通院回数は3〜5回程度が目安ですが、歯の状態によって回数が異なります。
長いと感じるかもしれませんが、途中で中断すると再発のリスクが高まり、抜歯が必要になることもあります。歯を守るためにも、最後まで適切に治療を受けることが大切です。
根管治療の期間が長くなる理由

根管治療は、歯の内部にある根管を清掃・消毒し、清潔な状態になるまで繰り返します。そのため、治療が長いと感じる患者さまは少なくありません。
以下に、根管治療の期間が長くなる主な理由について解説します。
根管の形状が複雑
歯の根の形は一人ひとり異なります。なかには根管が細かく枝分かれしているなど、形状が複雑な方もいます。とくに、奥歯は根管の数が多く、形状も複雑になりやすいため、前歯と比較して治療に時間がかかることが一般的です。
細い根管の奥までしっかりと清掃しなければ、細菌が残って再感染するリスクがあるため、しっかりと処置する必要があります。
感染の範囲が広い
虫歯が進行し、根管内に細菌が広がっていると、治療期間が長くなる傾向にあります。感染が根の先まで達している場合は、清潔な状態にするまでに何度も消毒を繰り返して細菌を完全に除去しなければならないためです。
また、根の先に膿がたまっているケースでは、炎症を抑える処置も必要になるため、さらに時間がかかる可能性が高いでしょう。
痛みや腫れがある
根管治療中に痛みや腫れが強い場合は、無理に治療を進めると症状が悪化することがあります。そのため、はじめに痛みや炎症を抑える処置を実施し、症状が落ち着いてから治療を再開するケースも少なくありません。
この場合、根管治療に取り掛かるまでに時間がかかるので、治療が終わるまでの期間も長くなります。
治療の間隔が空きすぎる
根管治療は複数回の通院が必要なため、仕事や予定の都合で治療の間隔が空いてしまう方もいるでしょう。
しかし、治療の間隔が空きすぎると、適切なタイミングで消毒ができず完了までに余計な時間がかかることがあります。また、途中で治療を中断すると細菌が繁殖し、再感染のリスクが高まるため、結果的に治療期間がさらに長引く可能性もあります。
スムーズに治療を進めるためには、なるべく歯科医師に指示された受診の間隔を守ることが大切です。
治療期間が長くても根管治療を受けたほうがよい理由

根管治療は複数回の通院が必要です。1ヶ月ほどかかることもあるので、途中で治療をやめたいと思ってしまう方も少なくないでしょう。
しかし、治療を途中でやめてしまうと、歯の健康に大きな影響を及ぼす可能性があります。以下に、治療期間が長くても根管治療を最後まで受けるべき理由を解説します。
歯を残せる可能性が高くなる
根管治療は、抜歯を避けるために必要な治療です。歯の神経が炎症を起こしたり感染が進行していても、根管治療をおこなえば歯を残せる可能性があります。
抜歯になると、失った歯を補うためにブリッジや入れ歯・インプラントなどの治療が必要になり、費用や治療期間の負担がさらに増えることになるでしょう。患者さまの負担を減らすために、根管治療は必要なのです。
再発するリスクを防ぐ
治療を途中でやめると、根管内に細菌や汚れが残った状態になるため、強い痛みや腫れを繰り返す原因となります。一時的に痛みが引いたとしても、再び症状が悪化するケースは少なくありません。
歯の根まで感染が広がると根の先に膿がたまり、大きな炎症を引き起こすこともあります。
全身の健康にも影響を及ぼす可能性がある
根管治療を中断して感染が広がると、歯の周囲だけでなく全身の健康にも悪影響を及ぼすことがあります。免疫力が低下している方や持病がある方は、根管内の細菌が血管を通じて全身に広がるリスクがあるため注意が必要です。
期間が延びるほど治療が困難になる
根管治療を途中でやめると、細菌が増殖し清潔な状態にすることが難しくなります。感染が進行して通常の根管治療では対応できないと判断された場合は、外科的な処置が必要になることもあるでしょう。
早めに適切な処置を受けることが、治療期間を長くさせないために重要です。
根管治療の流れ

根管治療は、さまざまな工程を踏んで進められます。以下に、根管治療の一般的な流れを解説します。
- 診査・診断
- 神経除去
- 根管内の洗浄・消毒
- 根管充填
- 被せ物の装着
それぞれ詳しく解説します。
①診査・診断
視診をおこないレントゲンを撮影して、歯の内部の状態を詳しく確認します。レントゲンを撮影して虫歯の進行度や根管の形状を把握して、治療計画を策定する流れが一般的です。
痛みが強い場合は、応急処置として炎症を抑える治療をおこなうこともあるでしょう。
②神経除去
局所麻酔をおこなって、虫歯や感染した神経を取り除きます。専用の器具を使い、根管内の細菌や汚染組織をしっかりと除去する必要があります。
③根管内の洗浄・消毒
根管内に細菌が残らないよう、器具や薬剤を使用して清掃をおこない消毒をします。感染の程度によっては、複数回の消毒が必要になります。この場合も、毎回薬剤を詰めて密封します。
④根管充填
根管内の感染がなくなったことを確認したら、根管に隙間が生じないように薬剤を詰めて密封します。しっかりと密封することで細菌の再侵入を防ぎ、治療した歯を長く保つことができます。
根管の先端まで薬剤が充填できているか確認するために、レントゲンを撮影することが多いです。
⑤被せ物の装着
根管治療を終えた歯は、神経を失い枯れ木のようにもろくなっている状態です。噛む機能を回復させるためには、土台を立てて被せ物を装着し、歯の強度を保つ必要があります。
被せ物で歯を補強することで、噛む力にも耐えられるようになります。
まとめ

根管治療が長い理由は、根管の細菌を完全に除去し、歯をできるだけ長持ちさせるためです。途中で治療をやめると再感染や抜歯のリスクが高まります。一度根管治療をした歯は再治療が難しくなるため、最後までしっかり治療を受けることが重要です。
治療中に気になることがあれば、遠慮なく質問するようにしましょう。違和感や痛みを感じたら、速やかに歯科医院を受診して確認してもらってください。
根管治療を検討されている方は、東京都板橋区大和町、都営三田線「板橋本町駅」より徒歩30秒にある歯医者「アース歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。
当院は、虫歯・歯周病治療や根管治療、入れ歯・ブリッジ治療などの保険診療だけでなく、インプラント、ホワイトニング、矯正歯科などの自由診療にも力を入れています。ホームページはこちら、ネット診療予約も行っていますので、ぜひご活用ください。